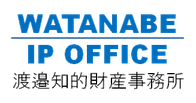最近、海外で面白い判決が出ました。テーマは「AIは発明者となりうるか?」です。
オーストラリアでは「AIは発明者となりうる」と判事されました。
一方、アメリカとイギリスでは「AIは発明者となり得ない」との判決です。
いずれも判決が確定したわけではないので、現時点では決まったわけではありません。
ちなみに、日本ではどうでしょうか?現行の特許法では「発明をした『者』は、… 特許を受けることができる」と規定されており、「者」とは「人間」であると解釈されています。このため、まず間違いなく「AIは発明者となり得ない」と判断されると思います。
ただ、AI技術がどんどん発達している昨今、「AIは発明者となりうるか?」との問いは、近い将来、特許制度の根幹を揺るがす議論になるかもしれません。
既に著作権の世界では、数年前から活発に議論されてきています。AIが書いた小説、AIが描いたマンガ、AIが作曲した音楽、知性より感性の著作の世界では、その例の枚挙にいとまがありません。既に、現実となりつつあるからです。
今のところ「AI自体に著作権を与える必要は無い」との立場が主流です。それでは、「AIによる著作物(AIが書いた小説など)の著作権は誰のものか?」については様々な立場があります。AIを開発した人のもの?AIを使っている人のもの?誰のものでもない?
知的財産権がお金に結びつく現代、これは重要な問題です。特許権に置き換えると、例えば「AIが新型コロナの特効薬を開発した」と考えてみると良く分かります。特効薬を販売して得る巨額の富は、AIを開発した会社のものか?AIを使った製薬会社のものか?それとも、誰のものでもないので特許を気にせず万人が恩恵にあずかることができるのか?
世の中を変える大きな問いかけが身近に迫ってきています。
(メルマガ「IPビジネスだより 2021年9月号」から転載)