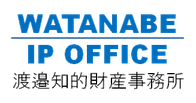商標「ゆっくり茶番劇」を巡る最近の事件、ご存知ですか?
ネットの世界で議論が交わされている事件ですが、地上波テレビのニュースでも取り上げられました。次のサイト(日テレNEWS)をご覧いただくと事件の概要が分かります。
創作者が「どうぞ自由に使ってください」と言っているゲーム(東方Project)キャラクターを使用して第三者が制作した動画が「ゆっくり動画」と呼ばれています。この「ゆっくり動画」のひとつのカテゴリーが「ゆっくり茶番劇」で、この言葉はSNSでのタグ付けなどに利用されています。
今回、「ゆっくり茶番劇」という「言葉(文字)」をキャラクター創作者でない第三者が商標登録をし、さらに、使用料を求めることをSNSで宣言したことがネット界隈で議論になりました。
上述のニュースの中でも説明されているように、商標制度としては創作者以外の第三者が商標登録を行うこと自体はなんら法的に問題ありません。商慣習に照らしてどうなのかといった問題になります。
では、この問題を少し大局的に眺めてみましょう。
前述のニュースで「日本の制度として認められている」との解説がありました。この部分のみを見ると「日本の制度はおかしい!」といった声が聞こえてきそうですが、実は、この早い者勝ちルールは、世界中どこに行っても原則同じです。日本だけのルールというわけではありません。
さらに、商標制度は、国ごとに独立です。つまり、日本で「ゆっくり茶番劇」を商標登録したとしても、外国に権利は及びません。例えば、米国や中国で「ゆっくり茶番劇」を他人が使ってもまったく影響ありません。
もうひとつ、今回の特徴は「ネット世界」で起きた事件だということです。前述のニュースを見直してみると、「『ゆっくり』というキーワードをもっとユーチューブで調べられていたら」と、代理人の弁理士がテレビ局のインタビューに答えていることに気づきます。
商標制度では、「他人の商品やサービスを示すものと需要者の間に広く認識」されている商標は登録されません。しかし、「需要者の間に広く認識」とは誰でも知っているレベルを求められ、ネット界隈でのみ知られている今回の状況がこれにあたるかといえば難しいでしょう。事実、多くの方は「ゆっくり茶番劇」と聞いても「それは何?」といった反応ではないでしょうか。
さて、世界中で商標は早い者勝ち、商標制度は国ごと、ネット世界。このように眺めていくと次の疑問が湧いてきます。
「国境のないネット世界で商標はどのように保護されるのか?」
実は、この問題は以前から指摘されながら、なかなか解決に至っていない課題です。一方で、メタバースなどネット上の仮想空間で行うビジネスモデルはどんどん進歩しています。
現在の商標制度は、産業革命以降の国の産業振興に起源をもちます。実体のある商品が市場で流通するモデルに基づいて制度設計がされています。ネット世界に適用するには、少々ひずみが出てきています。
ネット世界のビジネスが広がる今、商標制度の未来について国際的な場で活発に議論がなされています。世界で一つの制度を目指すのか?NTFのような技術に頼るのか?
「ゆっくり茶番劇」の事件は、大きな流れの中で顕在化した現在の商標制度のほころびを示すひとつの事象と見ることもできるでしょう。
(メルマガ「IPビジネスだより 2022年5月号」から転載)