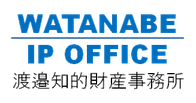「AIは発明者になれるのか?」
この問いかけにひとつの答えを示すような出来事が最近相次ぎました。
ひとつは、東京地裁が今月出した判決です。発明者は人間に限定されると判示しました。
(出典:日本経済新聞 2024.5.17)
これは、AIを発明者とした特許出願を特許庁が却下したことに対する裁判です。日本の特許法では発明者は人に限定されているので、この判決自体は当然の結論といえるでしょう。
ただ、興味深いのは、記事によれば「現行法の解釈では『AIがもたらす社会経済構造の変化を踏まえた的確な結論を導き得ない』と指摘。AIに関する制度設計は『国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることが相当』と言及した」とのくだりです。
これは、地裁レベルではあるものの、「現在の特許法ではAIが発明者にはなりえないが、将来的には適切な立法プロセスをとれば変わるかもしれない」と一歩踏み込んだということになります。
では、現時点で国は、この点をどのように考えているのでしょうか。これがふたつ目のニュース「知的財産推進計画2024」です。
(出典:読売新聞 2024.5.24)
「知的財産推進計画」は、毎年発表される知的財産戦略に関する政府見解です。今年の知的財産推進計画に「AI創作物であっても発明者は人であり、AIは補助的な役割にすぎない」と明記されることになりました。東京地裁の判決と同様の見解です。
このように現時点では、立法(政府)、司法(裁判所)、行政(特許庁)の足並みはそろっているといえるでしょう。また、これは世界的にみても同様の流れです。
ただ、2045年問題ともいわれる「2045年にはAI技術がシンギュラリティを迎えて人間の知能を越える」ことが現実になるのであれば、今後、知的財産の扱いをどのように考えていくかは喫緊の課題となっていくことでしょう。
世界の動向を眺めつつ、日本だけが後れをとるようなことがない対応が求められます。
(メルマガ「IPビジネスだより 2024年5月号」から転載)