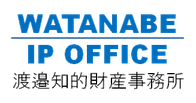「iPS細胞関連特許 開発研究者 企業と和解 一部治療で利用可能に」との報道がありました。(出典:NHK 2024.5.31)
この報道によると「iPS細胞から網膜の組織を作る技術の特許をめぐり、技術を開発した研究者が、特許権を持つ企業などに対して利用を認めるよう求めていたことについて、研究者側は30日、企業との間で和解が成立し、一部の治療について特許が利用できるようになったと発表しました」とのこと。
詳しい経緯は、記事を参照いただければと思いますが、簡単にまとめるならば、企業と一緒に研究・開発をしていた研究者が、研究成果をなかなか世に出さない企業に業を煮やして、自分たちでやるから特許発明を使わせてほしいと申し出たところ・・・といった事件です。
特許権は、発明の実施を独占する強力な権利ですから、第三者から「使わせてほしい」との申し出があっても断ることができます。しかし、それでは世のためにならないといった場合もあるかもしれません。
そこで、この研究者グループが申し立てたのが「裁定」です。記事では、裁定について「特許権を持つ人の同意無しに国が第三者に利用を認める」制度と説明しています。
この裁定、いわゆる「伝家の宝刀」とも呼ばれています。実際に裁定が請求される事態もまれですし、裁定が下ったといった例も見当たらないといって過言ではないでしょう。その意味では、今回の事態は、ある意味、画期的ともいえます。
裁定は、本来、実施を独占できる特許権について、第三者に実施を認めるわけですから、どのような場合でもよいわけではありません。法律で厳密に決まっています。今回は、「特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるとき」に認められる裁定を請求しています。
すなわち、特許を活用してiPS細胞から網膜の組織を作る技術を世に広めていくことは、公共の利益のため特に必要だと主張したわけです。
裁定では、特許庁ではなく、経済産業大臣が「特許発明の実施が公共の利益のため特に必要である」かどうかを判断することになります。すなわち、発明の独占といった個人や企業の権利の一部を、公共の利益の名のもとに第三者に認めるのは適当かどうかについて、より高い見地から判断をすることになります。
今回、裁定が下る前に両者での和解が成立しましたが、「自発的解決で新たな事業が実施されることは、特許法の趣旨に合致する」とのコメントが経済産業大臣から出されたのも、このような制度背景があってのことでしょう。
「経産相『法の趣旨に合致』iPS網膜特許和解で」(出典:産経新聞 2024.5.31)
特許法は、産業の発達を目的としますが、公益性とのバランスは常に考えて運用されます。今後また裁定が求められるような事態が起きるか分かりませんが、特許をとれば、どんな場合でもすべて独占とはいかないことは念頭に置くべきでしょう。
(メルマガ「IPビジネスだより 2024年6月号」から転載)