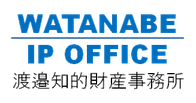「キリンによる買収劇、狙いは『ファンケルの特許』」とのコラムを見つけました。
(出典:ビジネスインサイダー 2024.7.25)
先月、キリンホールディングスは、ファンケルを完全子会社にすることを目的として株式の公開買付け(TOB)を行うと発表しました。2,000億円程度のお金が動く見込みだそうです。このコラムによると、その狙いのひとつがファンケルの特許を手に入れることだと論じています。
キリングループのライフサイエンス事業の中核企業は協和発酵バイオです。コラムによれば、協和発酵バイオの特許件数は微増にとどまる一方で、ファンケルの特許件数は協和発酵バイオの4倍とのこと。加えて、両社の研究分野も重なりが少ないことから相乗効果が期待できるようです。
もちろん、特許は数が多ければよいといった単純なものではありません。どのような分野で、どのような内容の技術を押さえている特許なのかは重要です。
一方で、ビジネスプランを考えたときに、自社で不足する技術を他社が既に持っているのであれば、その会社ごと自分たちに取り込むことは十分に検討に値する戦略です。この際、特許は必ず「公開」されていることは、検討を進めるにあたって有効です。自社が不足した資源を持っている企業を探すためのデータを誰でも自由に見ることができるからです。
このように、特許の情報が公開されていることは、必要な技術をもつピースを探すことに役立つばかりではありません。公開されている特許情報に、新製品開発のヒントが隠れていることもあるでしょう。また、特許を調べることで競合企業の動向を知ることもできるでしょう。もっとマクロに調査をすれば、業界の動向を眺めることもできます。
特許制度には「独占」と「公開」の2つの側面があります。一定期間、発明の独占を認める代わりに、その内容を広く公開しなければならないというものです。
特許というと、どうしても「独占」の側面に目がいってしまいがちです。しかし、特許のもうひとつの側面である「公開」に目を向けると、特許情報が宝の山に見えてくるかもしれません。
(メルマガ「IPビジネスだより 2024年7月号」から転載)