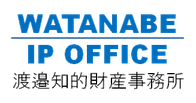2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス法)が施行されました。
IPビジネスだよりの読者の方々にも、フリーランス法で保護の対象となる方も多数おいでかと思います。従来の下請法と比べると資本要件がなくなるなど保護の対象が拡大されています。
そんな中、「著作権トラブル『泣き寝入りしない』、フリーランス法を生かすには」という記事が目に留まりました。(出典:朝日新聞デジタル 2024.11.18)
記事では、イラストレーターが「著作権の譲渡は希望しない」との条件のもと、仕事を受けて納品まで行ったものの、後から「著作権を譲渡してほしい」と言われて押し切られたといった事例が記載されています。
最近、私も、クリエイターの方々とお話しする機会があったのですが、上述のようなことは、業界では、いわゆる「あるある」のようです。上記事例では、契約書を交わしていなかったことも問題ですが、たとえ契約書があっても力関係で迫ってくるとの話はよく耳にするかもしれません。
記事によると、日本フリーランスリーグが行ったクリエイター調査では、契約書に入れるべき取決めについて「著作権・著作者隣接権の扱い」が非常に高く78%だったそうです。
とはいえ、契約書のどこをチェックすればよいのか難しいですよね。そこで、少なくとも気を配るべき3つの文言(もしくは同じ趣旨を述べている文言)をご紹介します。
1.「一切の著作権(著作権法第27条、第28条の権利を含む)を譲渡する」
「著作権法第27条、28条の権利を含む」があるかどうかがポイントです。翻案権(第27条)、二次的著作物に関する権利(第28条)については、上記のように明示的に記載しないと譲渡が認められません。
2.「著作者人格権は行使しないものとする」
著作者人格権という権利は、名前の通り人格を守るため権利です。著作者(人格)に紐づく権利であるため、他の人に権利を譲ることはできません。契約で譲渡すると定めても無効となるため、上記のように権利行使しないといった取り決めが一般的になります。
3.「納品物に含まれる著作権のうち、受注者または第三者が本契約前から保有していた著作物の著作権は除く」
これは、「たとえ著作権を譲渡するにしても、すべてというわけではないですよ」という規定です。
これらの規定は、発注者側なのか、受注者(クリエイター)側なのかで有利・不利が逆転します。
紙幅の都合、詳細な解説は割愛しますが、契約を交わす際には、是非、ご自身で、その意味するところを調べ、確認し、納得したうえで契約されることをお勧めします。
フリーランス法が施行されたこの機会に、是非、検討してみてください。
(メルマガ「IPビジネスだより 2024年11月号」から転載)