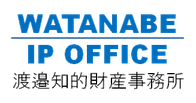「AI開発者にも特許権、発明に利用なら対価 政府検討」との報道がありました。
(出典:経済産業省 2025.1.14)
これについては、城内科学技術大臣も1月17日の定例記者会見の質疑応答の中で触れて、今年6月頃を目標に策定を進めている「知的財産推進計画2025」に反映する方針と述べています。記者会見の様子は、内閣府のサイトで動画が公開されています。
(出典:政府広報オンライン 2025.1.17)
さて、このニュースが注目される点について分かりやすくご説明いたしましょう。
従来から「AIを使って発明した物は特許がとれるのか?」といった議論はなされてきました。前述の「知的財産推進計画2025」の検討でも大きなテーマとなっています。これについては、基本的に、AIを使って発明した物にも特許性は認められるとし、現在は、そのための条件(AIを誰が、どのように使ったか、など)が議論の中心になっています。
一方、今回の報道は、これと異なります。次のような場合を想定しています。
「Aさんが開発したAIを使って、Bさんが発明した物(X)に特許を認められた。この場合、Aさん(AI開発者)もBさんと一緒にXの発明をしたといえるのではないか」といった場面です。
日経の記事タイトル「AI開発者にも特許権、発明に利用なら対価 政府検討」とは、言葉を補足すると、「特許発明の成立にAIが深く関与しているのであれば、そのAIを開発した開発者にも特許権を与えてもよいのではないか?また、特許発明を行うために必ず使わなければならないAIがあるのであれば、そのAIを開発した開発者に対価を支払うことにしてもよいのではないか?といった論点について政府が検討すると明言した」となるでしょう。
もちろん、どんな場合でもAI開発者に特許権が与えられるといったわけではなく、特許発明への貢献度などが評価されることになるでしょう。その際の基準をどうするかについて国の判断が示されるということです。
日常的にAIを活用する時代です。発明する際にChatGPTを使ったからといって、OpenAIが特許権を主張してきたら困ってしまいます。その一方で、特定分野の研究データなどをAIに学習させてファインチューニング(追加学習)を行った場合、その追加学習があったからこそ発明が完成したのであれば、その開発を行ったAI開発者も特許権を認めるべきではないかいった意見も理解できます。
どのような判断基準が示されるか興味深いところですが、AIエンジニアにとってビジネスチャンスが拡大することは間違いありません。
6月予定の「知的財産推進計画2025」に注目です。
(メルマガ「IPビジネスだより 2025年1月号」から転載)